デジタル広告業界が今、大きな変容を迎えようとしています。
サードパーティクッキーの規制強化、広告主のブランドセーフティ意識の高まり、ユーザーの広告疲れなど、さまざまな要因が絡み合い、もはや従来のデジタル広告戦略の限界が見え始めてきた昨今。
新たな広告手法として台頭しつつあるのが、「デジタルリテールメディア」の活用です。
2025年7月25日、Rokt、楽天、メルカリの3社は共同で、デジタルリテールメディアの未来を展望するカンファレンス「Digital Retail Media Conference 2025」を開催しました。
近年注目を集めているものの、正確な情報が手に入りにくいこの領域。日本における最新の状況を踏まえ、どうしたら効果的に取り入れることができるのか。現役のマーケターにすぐに役立つ情報が、業界をリードする3社の知見と共に紹介されました。
高まる期待とともに始まったカンファレンス
「Digital Retail Media Conference 2025」は、Rokt、楽天、メルカリ、3社の代表による言葉から始まりました。Rokt合同会社のHead of Japan、三島健は、カンファレンスに対する期待を以下のように語ります。

「現在、日本の総広告費の約15%が、デジタルリテールメディアに投資されています。しかし、これまでこの領域について議論する場は多くありませんでした。情報が溢れ、消費者のタッチポイントが変化する中、リテールメディアについてしっかりと深掘りする時間が必要です。Rokt、楽天、メルカリのワンチームで、本日は実りあるカンファレンスにしたいと思います」。
楽天グループ株式会社のアカウントイノベーションオフィス ジェネラルマネージャー、堀川直裕氏は、楽天のリテールメディアに対する意気込みを力を込めて述べました。

「私たち楽天グループには、お客様とのタッチポイントとなる70を超えるサービスと、蓄積した豊富なファーストパーティデータがあります。それらを活かせるリテールメディアは、次なるマーケティングの主戦場だと捉えており、全社をあげて強化していこうとしています。”日本のリテールメディアの未来像”を、本日はこの場所で皆様とともに考えていきたいと思います」。
株式会社メルカリのHead of Ads Business、赤星大偉氏は、リテールメディアのエコシステムの中でメルカリが果たせる役割に触れて、カンファレンスへの想いを語りました。

「賢くモノを選び、長く使い続けるという新しい消費観の中で、どのようにブランドが消費者とコミュニケーションしていくべきか。リテールメディアのさらなる発展に、”循環型社会への貢献”をミッションに掲げるメルカリは貢献できると信じています。メルカリも、リテールメディアのエコシステムの一員として、皆様とともに成長していきたいと考えています」。
真夏の東京、200名近いマーケターが集まった本カンファレンスは、リテールメディアに対する大きな期待とともに幕を開けました。
なぜ今、リテールメディアなのか:買い場中心の再設計が生む、広告のパラダイムシフト
そもそも、リテールメディアはどのような特徴を持ち、一体どのようなポテンシャルを秘めているのでしょうか。
カンファレンス前半では、特別ゲストによる「リテールメディアの可能性」に関する講演が行われました。

「これからは、”買い場”中心の設計が重要だと考えています」。
そう語るのは、長年マーケティング領域の第一線で活躍している、株式会社Preferred Networksのエグゼクティブアドバイザー、富永朋信氏です。
富永氏は、”接触態度(メディアごとに異なる消費者とコミュニケーションの関係性)”を鍵に、テレビとデジタル広告の違いから話を始めました。
テレビCMには15秒という制約の中で完成されたフォーマットがあり、視聴者と発信側の間で”15秒間広告を見続ける”という接触・理解の作法が共有されていました。一方でデジタル広告は媒体・フォーマットが無数に分散し、統一的な接触態度が育っていないため、行動変容につながりにくい側面があると指摘します。
そこで富永氏が提唱するのが、「買い場を中心にしたマーケティングの再設計」です。
スーパーマーケットを想像してみてください。「魅力的な商品を見つけて、衝動買いする」。このような購買体験は往々にして発生しますが、そこでは複雑なファネル設計は意味をなさず、棚に並んだ商品の魅力が顧客の購買をドライブしています。接触態度も確立されておらず、複雑化している現代の広告だからこそ、「店頭でどうやって顧客を魅了するか」の視点に今一度立ち帰り、マーケティング戦略を設計していくべきだと富永氏は説きました。
それをわかりやすく展開できるのが、リテールメディアです。EC上で売り場や商品の魅力を発信し、顧客とのコミュニケーションを最大化するリテールメディアでは、まさに”買い場”を中心にしたマーケティングが可能です。

富永氏は、実店舗の原則「製品+ステージ(棚)+看板(POP)=商品」をECにも援用すべきだと提案します。棚やPOPは、”おすすめ”を直感的に伝える仕掛けです。協調フィルタリングを中心としたリコメンデーションによる購買経路だけでなく、実店舗のマーチャンダイジングシステムも取り入れたECサイトの構築には、大きな可能性が眠っていると述べました。
さらに、これまで単に消費者に対して商品を紹介する役割であった広告が、消費者に本当に必要なものを届ける存在へと変容していくビジョンも提示されました。ポイントは、「顧客がどのような目的で店を訪れているか」と、「どのようなものを実際に買ったか」を分析、把握することです。
ユーザーデータをつぶさに計測、観察できるリテールメディアは、顧客一人一人に対して固有の線を結べます。そしてその世界観における”広告”とは、ブランドと顧客の関係性をマネージしていく手段となるのです。
数字が示す、リテールメディア市場の成長:広告の大きな潮流の向かう先
では、リテールメディア市場は今、どのような状況にあるのでしょうか。
株式会社CARTA ZERO、ソリューションディベロップメント局 局長である田中慎介氏が、データをもとに紐解きました。
.png)
デジタルリテールメディアの市場規模は、2025年時点で6,000億円弱(日本の総広告費の約15%)に達し、2028年には1兆円超へ。年率20〜25%程度で拡大していくと示されました。昨年のデジタル広告費全体の伸び率が9.6%であったことを考えると、リテールメディアが成長を牽引する存在になっていることがわかります。
ではなぜデジタルリテールメディアは急成長しているのでしょうか。田中氏は、「データプライバシーの潮流」、「”人”が動きやすい広告」、「EC消費の増加」の3点を指摘します。

まず、世界的にデータプライバシー保護への関心が高まる中で、ターゲティング広告に利用されてきたIDへの規制が進み、ブラウザやアプリを横断したターゲティングでリーチできる人数が減少しています。こうした状況を受け、より高いパフォーマンスを求める広告主が、自社会員データなどのファーストパーティデータを活用できるリテールメディアへと移行している背景が紹介されました。
さらに、ファーストパーティーデータを活用することで、ユーザーの興味・関心に即した発信が可能になり、ECの中に自然に溶け込むデザインはショッピング体験を損なうことなく効果を発揮。こうした特性から、リテールメディアは有力な広告手法として注目を集めています。加えて、社会全体でEC消費が拡大し、それに伴って出品者や広告主が増えていることも、デジタルリテールメディアへの投資額を押し上げ、市場成長を後押しする要因となっています。
デジタル広告の三大課題を解決する、リテールメディア
ここまでで、丁寧にリテールメディアのポテンシャルが整理された本カンファレンス。後半ではさらに具体的なトピックへと議論が進みました。
次のセッションでは、Rokt、楽天、メルカリの3社が、リテールメディアが現在のデジタル広告の課題をどのように解決することができるのか、パネルディスカッション形式で話されました。

セッション冒頭で提示されたのは、既存デジタル広告の抱える三大課題です。広告主400名と一般生活者1000名を対象にRoktが実施した、デジタル広告とリテールメディアに関する意識調査で、「ブランドセーフティーとアドフラウドの課題」、「ターゲティング精度の低下」、「広告のノイズ化」という3つの課題が浮き彫りになりました。3社は、リテールメディアがこれらの課題への解決策となると語ります。
「ブランドセーフティー」とは、広告主がブランドイメージを保護するために、不適切なコンテンツやサイトに広告を出さないようにする取り組みです。「アドフラウド」は、ボットなどが意図的に引き起こす不正クリックや不正インプレッションを指しています。
.png)
調査によると、デジタル広告の責任者の76%が自社のオンライン広告が不適切なコンテンツ上に表示されることに対する懸念を、72.4%がアドフラウドへの懸念を表明しています。一方一般消費者の85%は、広告が「怪しい/不快な/品のない」サイトに掲載されていた場合、その広告主や商品への印象が悪化すると答えており、世間の意識の高まりが示唆されました。
メルカリの赤星氏は、そもそもの仕組みの違いが、こうしたリスクを回避すると語ります。
「リテールメディアは、一次プラットフォーマーが自らのサービスもしくはアプリ上で広告を配信するものであるため、アドネットワークとは全く異なる配信の仕組みになっています。実際に我々のmercari Adsも、メルカリのアプリとWebを中心に広告配信をしています」。
では、「ターゲティング精度の低下」についてはどうでしょうか。Roktの調査では、デジタル広告の責任者の69.9%がこうした課題感を表明し、一般消費者の79.2%が自分に関係のない広告を見せられた時に不快感を感じると答えています。サードパーティクッキーの規制などによるターゲティング精度の低下は、広告主、消費者にとって大きな課題となっています。
.png)
楽天グループ株式会社、アカウントイノベーションオフィス ヴァイスジェネラルマネージャーの秦俊輔氏は、こうした課題もリテールメディアなら解決できると話します。
「従来の基本戦略が崩れている今、ファーストパーティデータ(購買関連情報)を活用して、その顧客が何を求めているのか判別し、適切な広告を出せるリテールメディアには大きなアドバンテージがあります。さらに、購買意識が高まっている状況で、その人におすすめの商品を提示できるので、それ自体がコンテンツ化し、消費者にとっても邪魔にならないコミュニケーションができるのもメリットです」。
最後に、現在の業界が抱える深刻な課題、「広告のノイズ化」についても議論されました。デジタル広告の責任者の74%が広告疲れや広告離れが要因で広告施策の効果が落ちてきていると感じており、一般消費者の81%も、広告が自分の行動を妨げたり邪魔になったことで、その広告主やサービスに対してマイナスの印象を持ったことがあると回答しています。
.png)
Roktの三島は、広告がノイズにならないためには、「タイミング」が重要であると語ります。
「広告を配信する”タイミング”も、重要な要素だと考えています。Roktが提供しているソリューションは、ユーザーが購入した直後のタイミングでオファーを提示します。受け手が最も感情が高まっているタイミングで、その人にとって有益なオファーを出せれば、消費者、広告主双方に有意義な体験となるはずです」。
成功事例から考える、デジタルリテールメディアの明日から使えるヒント
最後のセッションでは、3社によるリテールメディアの成功事例が紹介されました。
楽天:ブランドページを起点に、買い場中心のマーケティング設計を実現
楽天が展開するのは、70以上のサービスを横断して蓄積されたファーストパーティデータを活用した、フルファネルソリューションです。軸となるのは「ブランドページ」。ここを“買い場”として設計することで、購買に直結するコミュニケーションを可能にしています。
楽天グループ株式会社 アカウントイノベーションオフィス シニアマネージャーの浅貝健人氏は、次のように語ります。
「楽天のブランドページは、商品に興味を持つ潜在顧客をデータから選定し、そのユーザーを検討・購入へ導く導線を設計しています。施策後の行動データを分析し、ページを最適化するところまで一貫して対応できます。テレビCMなどのマスではリーチしづらかった層にも訴求でき、検討層を施策前の約2倍にまで拡大できた実績もあります」。

メルカリ:独自セグメンテーションで、効果の最大化を狙う
メルカリが展開する「mercari Ads」では、2つの広告フォーマット(検索連動型のダイナミック広告/ターゲティング可能なインフィード広告)を展開しています。強みは、購買意欲を精緻に見極めるセグメント設計にあります。
株式会社メルカリ JP Sales Specialistの酒向海氏は、次のように語ります。
「mercari Adsでは、検索だけでなく、”いいね”や、”コメント”をして価格交渉をしているユーザーにも絞って配信を行えます。これらの購買意欲が非常に強いユーザーにリーチすることで、CVRを6倍改善した事例もあります」。
また、特定タブの閲覧状況に基づいた配信も可能で、月間アクティブユーザー数(MAU)2,350万人というスケールも、圧倒的なデータ活用力を後押ししています。

Rokt:購入完了後の“瞬間”に、最適なオファーを届ける
Roktは、他2社とは異なり、自社メディアを持たない代わりにECサイトの「購入完了の瞬間」をネットワーク化し、広告主のオファーを届けています。
Rokt合同会社 Business Development Directorの大野皓平は、以下のようにRoktのソリューションを例えました。
「馴染みの服屋さんで、買い物のあとに店員さんからクーポンをもらう。Roktは、まさにそのような体験をオンラインで再現しています」。
Roktのプラットフォームでは、商品購入直後にのみ、オファーを表示。ファーストパーティデータと機械学習を組み合わせることにより、ユーザーが”お買い物モード”にある瞬間にオファーを届けます。CTR平均は5%という高い水準を記録しており、他媒体での出稿に比べ4.1倍のCTRや、CVRの33%改善などを実現した成功事例も紹介されました。

3社の事例が共通して示したのは、ファーストパーティデータを活用し、ユーザーごとの文脈に合った内容を、最適なタイミングで届けることの力です。精度あるターゲティングと設計によって、広告はノイズではなく、選ばれる体験へと進化しています。
次世代の広告メディアを作るために

目まぐるしく変化するデジタル広告の世界。規制強化やユーザーの意識変容に伴い、現在はこれまでの成功体験が通用しない、大きな転換点を迎えています。
その中で、広告主にとっては伝えたい価値を正しく届けられ、消費者にとっては自分にぴったりの選択肢と出会えるデジタルリテールメディアは、次の時代にふさわしい広告体験を提供する、新たなプラットフォームとして注目されています。
イベントの最後に、Roktの三島は以下のように締めくくりました。
「本日の議論を通じて、ステークホルダー同士の連携の重要性を改めて感じました。横断的な協力体制を築き、より良いリテールメディアを共に作っていく。今日の対話が、その一歩になることを願っています」。
日本でもいよいよ本格的に拡大フェーズを迎えているリテールメディア。より多くのプレイヤーが関わることで、すべての人にとって価値のある広告の未来が動き出します。




.jpg)

.jpg)
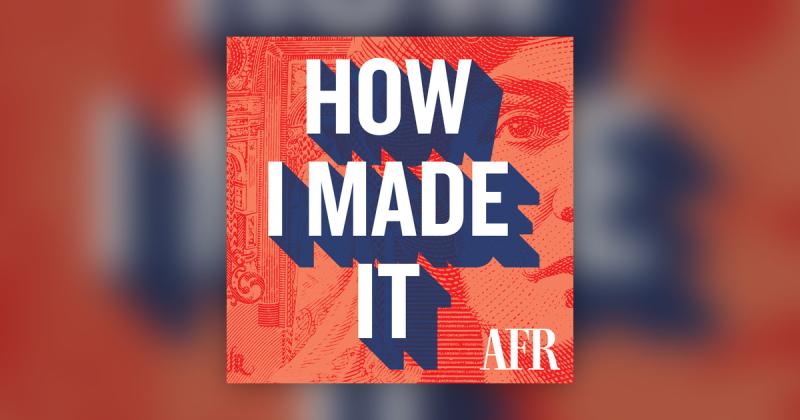

.png)